こんにちは、Tech Samuraiです!
前回の記事「ヤング率の早見表」では、材料そのものが持つ「硬さ(変形しにくさ)」について探検しました。しかし、製品の強度は、材料だけで決まるわけではありません。同じ材料、同じ重さでも、その「形状」によって、強度は劇的に変化します。
今回は、その最も代表的な例である「リブ(補強リブ)」を取り上げます。なぜ、プラスチック製品や金属部品に、あの薄い板状の補強(リブ)を付けるだけで、驚くほど頑丈になるのでしょうか?
この謎を解き明かすため、材料力学の基本であるフックの法則から始め、強度設計の鍵となる断面係数という考え方まで、その原理をステップバイステップで探検します!
全ての基本:「フックの法則」と応力・ひずみの関係
まず、材料に力が加わったときに、その内部で何が起こっているのかを見てみましょう。基本となるのがフックの法則です。
これは、材料がバネのように振る舞う範囲(弾性限度内)では、「変形のしやすさ(ひずみ)」と「内部で発生する抵抗力(応力)」は比例するという法則です。
数式で表すと以下のようになります。
$$ \sigma = E \cdot \epsilon $$
- σ(シグマ): 応力 (Stress) – 材料の内部で、変形に抵抗しようとする力。単位は [Pa] (パスカル)。
- E (イー): ヤング率 (Young’s modulus) – 材料固有の変形しにくさ(硬さ)を表す定数。
- ε
- (イプシロン): ひずみ (Strain) – 元の長さに対して、どれだけ変形したかの割合(単位なし)。
簡単に言えば、「硬い材料(Eが大きい)ほど、同じだけ変形(ひずみ)させたときに、より大きな力(応力)が発生する」ということです。
リブによる強度向上の「本質」
リブを設ける主な目的は、物体を曲げようとする力(曲げモーメント)に対する抵抗力、すなわち曲げ剛性を高めることです。
例えるなら… 1枚の紙は簡単に曲がりますが、その紙を「コの字」や「Tの字」に折ると、驚くほど曲げに強くなりますよね。リブは、これと全く同じ原理です。同じ材料の量でも、形状を変えることで強度を飛躍的に向上させます。
この「曲げにくさ」を数値化したものが、断面係数 (Z) です。曲げによって発生する最大の応力(曲げ応力)は、以下の式で計算できます。
$$ \sigma = \frac{M}{Z} $$
- σ: 曲げ応力 [Pa] – この値が、材料が耐えられる限界応力を超えると破壊されます。
- M: 曲げモーメント [N·m] – 物体を曲げようとする力の大きさ。
- Z: 断面係数 [m³] – 断面の形状だけで決まる、曲げにくさを示す指標。
この式が結論です。リブを付ける究極の目的は、この断面係数(Z)を大きくすることにあります。Zが大きくなれば、同じ力Mがかかっても、発生する応力σは小さくなり、結果として壊れにくくなるのです。
【計算例】リブの有無による断面係数の比較
では、なぜリブを付けると断面係数Zが大きくなるのでしょうか? 少しだけ計算の世界を覗いてみましょう。
断面係数Zは、断面二次モーメント (I) という、もう一つの形状指標から計算されます。
$$ Z = \frac{I}{y_{max}} $$
- I: 断面二次モーメント [m⁴] – これも断面形状だけで決まる、曲げにくさの指標。背の高い(高さ方向に厚みのある)形状ほど、この値は急激に大きくなります。
- ymax: 中立軸(曲げたときに伸びも縮みもしない中心線)から、断面の最も遠い点までの距離。
Case 1: リブのない板(単純な長方形)
幅b、高さhの長方形断面の場合、断面二次モーメントIと断面係数Zは、公式で簡単に計算できます。
$$ I_1 = \frac{b \cdot h^3}{12}, \quad Z_1 = \frac{b \cdot h^2}{6} $$
Case 2: リブを付けた板(T字形断面)
先ほどの板の下に、リブを追加したT字断面を考えます。計算は少し複雑になりますが、ポイントは、全体の断面二次モーメント I2 が、リブの分だけ I1 よりも必ず大きくなることです。
リブを付けると高さが増すため、中立軸から一番遠い点までの距離 ymax も変化しますが、一般的に断面二次モーモーメント I の増加率の方がはるかに大きいため(高さの3乗で効いてくるため)、結果として断面係数 Z2 は元の Z1 よりも大きくなります。
つまり、リブを付けて「背を高く」してあげることが、断面二次モーメントIを劇的に増加させ、結果として断面係数Zを大きくするのです。
まとめ
今回の探検をまとめると、以下のようになります。
- 材料の変形は、応力とひずみが比例するというフックの法則 (\( \sigma = E \epsilon \)) に従う。
- リブの役割は、断面の形状を工夫することで断面係数 (Z) を大きくし、曲げに対する強度を高めること。
- 曲げ応力は \( \sigma = M/Z \) で計算され、断面係数Zが大きいほど応力は小さくなる。
- リブによって断面の「背が高く」なると、断面二次モーメント (I) が大幅に増加し、結果として断面係数 (Z) が大きくなるため、強度が向上する。
設計の現場では、必要な強度から目標となる断面係数Zを算出し、それを満たすようなリブの高さや本数、配置を決定していく、という思考プロセスを辿ります。材料の知識と形状の知識、この両輪が揃って初めて、優れた設計が生まれるのです。
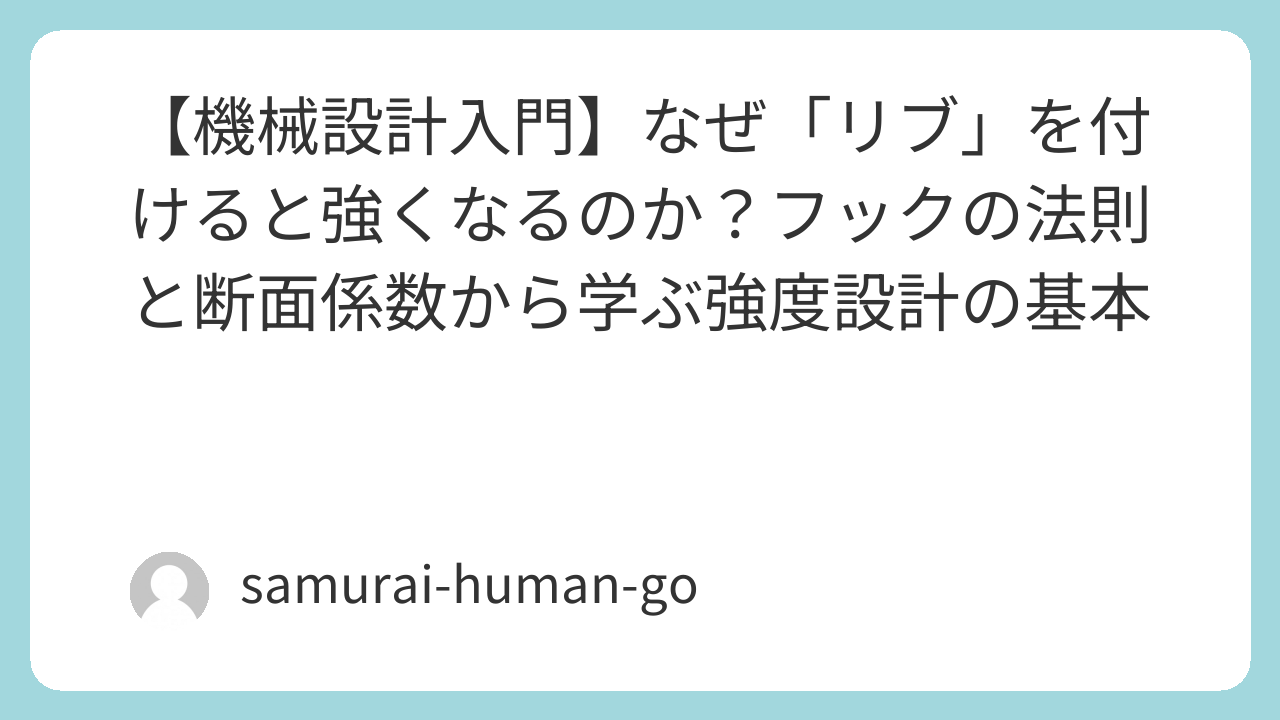
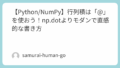
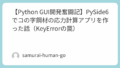
コメント