こんにちは、Tech Samuraiです!
私のブログはPythonを探検することがメインですが、プログラミングスキルは、現実世界の問題を解決するための強力なツールです。今回は少し趣向を変え、私が趣味で行っている「ものづくり」の中から、一つの製品を設計していく**思考のプロセス**を記録として共有したいと思います。
今回のプロジェクトは、**「80kgの小型ボートが秒速3mで岸壁に衝突した際の衝撃を和らげる、衝撃吸収アブソーバを3Dプリンタで自作する」**という、少し無謀な挑戦です。漠然とした目標から、物理計算と工学的なアイデアを駆使して、具体的な設計へと落とし込んでいく、リアルな試行錯誤の過程をご覧ください。

Step 1: 敵を知る – 衝撃エネルギーの算出
まず、アブソーバがどれだけのエネルギーを受け止める必要があるのか、物理の公式から算出します。これが全ての設計の基礎となります。
- 質量 (m): 80 kg
- 速度 (v): 3 m/s (時速10.8km、大人が早足で歩くくらいのスピード)
運動エネルギー(KE)の公式 KE = 1/2 * m * v² に当てはめて計算すると…
KE = 0.5 * 80 kg * (3 m/s)² = 360 ジュール(J)
これが、今回のアブソーバが吸収すべき目標エネルギー量です。衝撃の「力」は、この360Jのエネルギーを「どれだけ短い距離で」ゼロにするかで決まります。アブソーバの役割は、この吸収距離(ストローク)を長く確保し、ボート本体にかかる力のピーク値を下げることです。
Step 2: 最初のアイデアと課題 – 「バネ式」アブソーバ
最初に思いついたのは、二重の筒にバネを仕込む、シンプルな構造です。一度使ったら壊れてしまう緩衝材(ハニカム構造など)とは違い、繰り返し使えるのが大きなメリットです。
しかし、計算を進めると大きな課題が浮かび上がりました。バネはエネルギーを吸収して熱に変えるのではなく、位置エネルギーとして**「蓄える」**だけです。つまり、縮んだバネは、蓄えたエネルギーを解放して**「ボヨーン!」と強く跳ね返ってしまいます。** この反発は、ボートを危険な方向へ押し戻す二次被害につながる可能性があり、制御する必要があります。
Step 3: 反発を制す – 「ダンパー」機構の追加
バネの厄介な反発を抑えるために、自動車のサスペンションにも使われている**「ダンパー」**の概念を取り入れました。ダンパーは、運動エネルギーを摩擦熱などに変換して捨てることで、揺れや反発を滑らかに収束させる装置です。
3Dプリンタで実現可能な簡易ダンパーとして、2つの方式を検討しました。
- 摩擦ダンパー: シャフトと筒の間に摩擦材を挟み、その抵抗でエネルギーを消費させます。ギクシャクした動きを避けるため、摩擦材にはゴムよりも、TPUやPOM(ジュラコン®)、PTFE(テフロン®)といった、滑り特性を持つ素材が適しています。
- エアダンパー: 筒を密閉構造にし、ピストンで空気を圧縮して小さな穴から逃がす際の抵抗を利用します。よりスムーズな減衰が期待できます。
テフロンテープは日東や寺岡などの有名どころの物が使い勝手も良くオススメできます!
Step 4: 現実を知る – バネの性能計算
次に、手元にあるバネの性能から、具体的にどれくらいのエネルギーを吸収できるか計算しました。「2kgfの荷重で53mmから17mmまで縮む(=36mmストローク)」というバネの場合、1本あたりが吸収できるエネルギーは、わずか**0.35J**でした。目標の360Jには、全く歯が立ちません。
そこで、多数のバネを組み合わせる方法を検討しました。
- 並列接続: バネは硬くなり、同じストロークでより大きな力を受け止められる。
- 直列接続: バネは柔らかくなり、同じ力でより長いストロークを確保できる。
この組み合わせにより、アブソーバの「硬さ」と「ストローク」を調整できます。例えば、「7本並列にしたものを、2組直列に繋ぐ(計14本)」という構成では、吸収エネルギーは4.9J、必要な力は約14kgf、ストロークは72mmと計算できました。
Step 5: 解決策の構想 – ハイブリッドシステム
ここで、当初のアイデアを統合します。衝撃を「受け止める役」と「吸収する役」を分担させる、ハイブリッドシステムの構想です。
- 主役(バネ): 「7並列2直列」のバネが、衝撃の大部分 (4.9J) を長いストロークでしなやかに受け止めます。
- 助演(ダンパー): 3mm厚の天然ゴムシートなどをダンパーとして使い、バネが元に戻ろうとする反発エネルギーを吸収・減衰させます (約0.4J)。
この2つを組み合わせることで、合計約5.3Jのエネルギーに対応し、かつ反発の少ない理想的な**「バネ・マス・ダンパーシステム」**の基本形が完成しました。
Pythonへの橋渡し:計算とシミュレーション
今回のプロジェクトでは、様々な計算を手で行いました。しかし、バネの本数や配置、ストローク長など、パラメータを少し変えるたびに再計算するのは大変です。
このような試行錯誤こそ、**Pythonの得意分野**です。今後の記事では、今回行った物理計算をPythonスクリプトに落とし込み、`NumPy`や`Matplotlib`を使って、様々な条件下でのアブソーバの性能をシミュレーションする方法も探検してみたいと思います。
まとめ
当初の漠然とした「衝撃を和らげたい」という思いから、物理計算と工学的な試行錯誤を重ねることで、最終的には**「バネで衝撃を受け止め、ダンパーで反発を制す」**という、本格的な設計思想にたどり着きました。
目標の360Jを達成するには、このプロトタイプの構想をさらにスケールアップさせる必要がありますが、そのための明確な設計指針を得ることができました。ものづくりの楽しさは、まさにこの「思考のプロセス」そのものにあるのかもしれません。
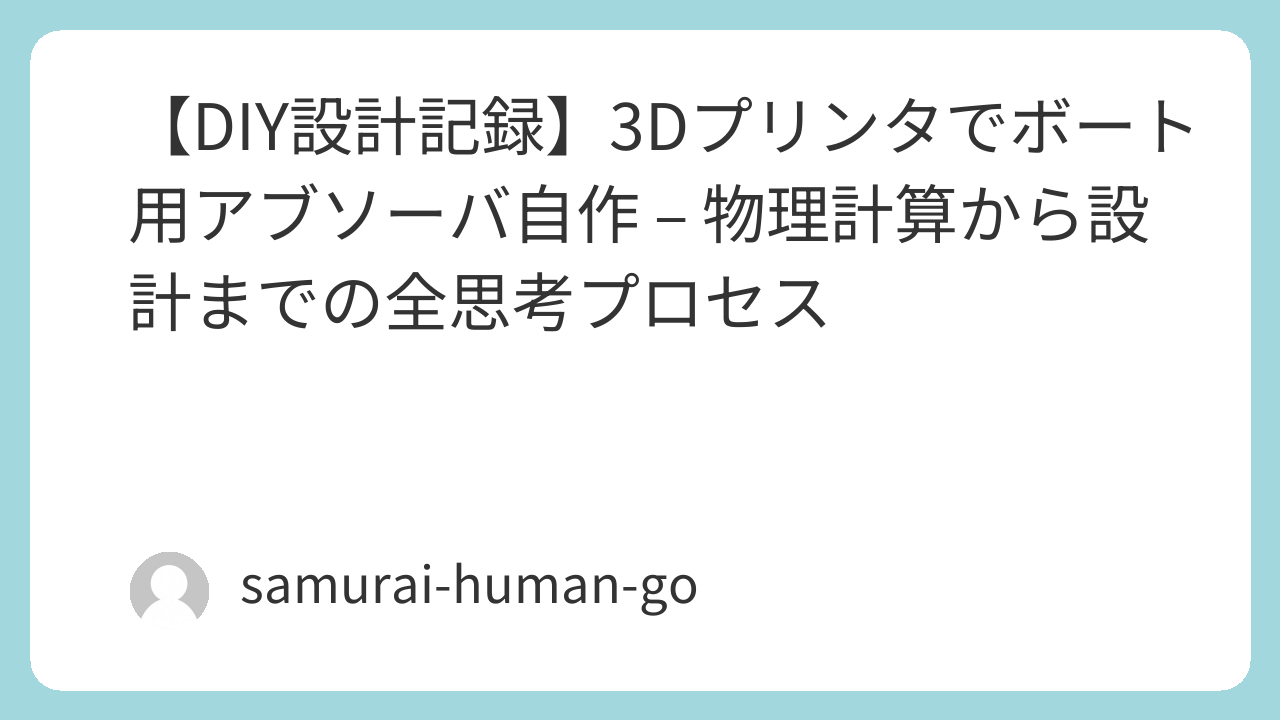
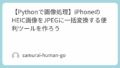
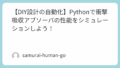
コメント